特定親族特別控除とは│要件や申告書の書き方など解説
更新日:2025年11月10日
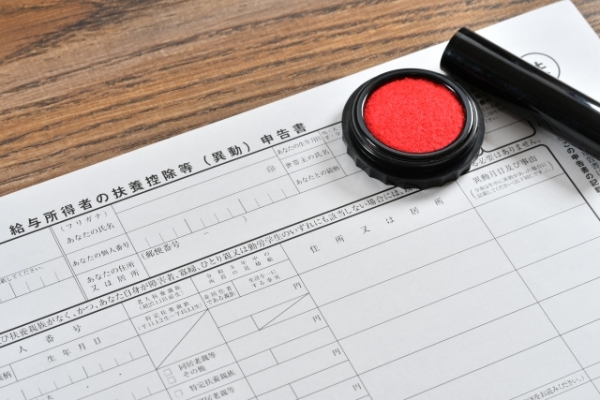
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
更新日:2025年11月10日
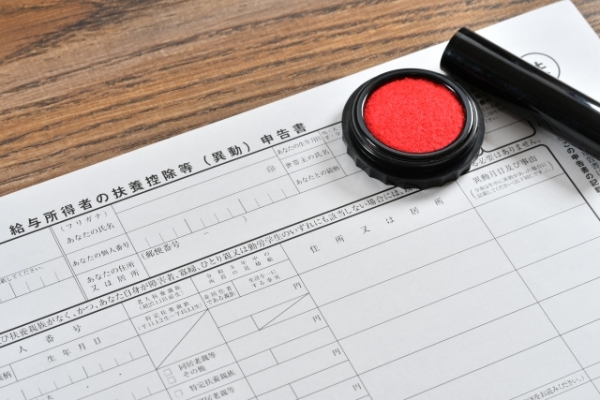
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
特定親族特別控除は、2025年度の税制改正で新たに導入される控除制度です。大学生世代の子どもを扶養する従業員を抱える経営者として、年末調整や給与計算への影響が気になる方も多いでしょう。制度の概要や申告書の書き方、システム対応、従業員への周知ポイントを押さえることが重要です。本記事では、基礎知識から実務対応まで詳しく解説します。
目次
特定親族特別控除とは?創設の背景
特定親族特別控除とは、大学生世代の子どもを扶養する世帯の税負担を軽減し、働き控えの解消を目的として創設された制度です。
従来の扶養控除では所得制限により控除が受けられないケースがありましたが、特定親族特別控除の創設によって条件が緩和されたため、親子双方にメリットがあります。
ここでは、制度の概要と創設の背景について見ていきましょう。
特定親族特別控除の概要
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を対象にしています。所得金額に応じて控除額が変動し、所得税で最大63万円が控除される仕組みです。
従来の扶養控除と比べ、所得要件が大きく緩和されています。所得税の適用開始は、2025年(令和7年)分からの適用です。
【特定親族特別控除額(所得税)】
(収入が給与だけの場合の収入金額※)
(123万円超〜150万円以下)
(150万円超〜155万円以下)
(155万円超〜160万円以下)
(160万円超〜165万円以下)
(165万円超〜170万円以下)
(170万円超〜175万円以下)
(175万円超〜180万円以下)
(180万円超〜185万円以下)
(185万円超〜188万円以下)
※特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
適用を受けるには、年末調整や確定申告での申告が必要です。アルバイト収入のある学生を扶養している世帯では、給与収入が123万円近くても控除対象となる場合があります。そのため、従業員には所得確認と申告を忘れないよう事前に呼びかけておくことが重要です。
参考)国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
特定親族特別控除創設の背景
特定親族特別控除の目的は、若年層の働き控えを解消し、人手不足を改善することです。
従来の特定扶養控除では、扶養親族の所得が103万円を1円でも超えると控除が受けられず、学生の就労抑制につながるケースがありました。
こうした課題を踏まえ、2025年の税制改正で制度が見直され、収入基準の緩和と新たな控除の導入により働き控えの是正が図られています。
特定親族特別控除と扶養控除の違い
これまで、19歳以上23歳未満(いわゆる大学生世代)の扶養親族は「特定扶養親族」として扱われ、以下の区分に該当していました。
参考)国税庁|No.1180 扶養控除
従来の制度では、扶養親族の所得上限に厳しい制約があったため、大学生世代の扶養親族を対象にした新たな仕組みとして「特定親族特別控除」が創設されました。
制度改正のポイント
従来の「特定扶養控除」では、合計所得金額の上限が48万円から58万円に引き上げられています。さらに、新設された「特定親族特別控除」では、次の新たな仕組みが導入されました。
引用)財務省|令和7年度税制改正
【特定扶養控除と特定親族特別控除の比較表】
(給与収入123万円以下)
(給与収入123万円超〜188万円以下)
・住民税:2026年(令和8年度)分〜
この改正により、大学生世代が一定の収入を得ても「103万円の壁」を気にせず働ける環境が整備されたといえるでしょう。これらの特定扶養控除の改正控除額と特定親族特別控除は、2025年12月の年末調整から適用されます。
特定親族特別控除の対象
特定親族特別控除の対象は、19歳以上23歳未満の大学生世代の親族のうち、合計所得金額が58万円を超え123万円以下(給与収入で123万円超〜188万円以下)の人です。
対象には、児童福祉法に基づき養育を委託された「里子」も含まれますが、納税者の配偶者や青色・白色専従者として事業に従事している親族は該当しません。
就職や進学、療養などの理由で別居している場合でも、納税者が生活費や学費、治療費などを負担していれば「生計を一にしている」と判断されます。
これらの要件を満たす場合、年末調整で控除を受けるには勤務先へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
特定親族特別控除の適用時期と申告書の書き方
特定親族特別控除を受けるには、制度の適用時期と申告書の記載方法を正しく理解しておきましょう。ここでは、適用スケジュールと申告手続きの流れを解説します。
【適用時期】
・2025年(令和7年)分の所得税から適用
↓
・2025年12月~:年末調整での適用開始
↓
・2026年1月~:給与・年金等の源泉徴収での適用開始
【年末調整と確定申告】
特定親族特別控除の年末調整で使用する様式は、以下の申告書との兼用です。
特定親族特別控除の記入欄は、下半分の箇所(図の赤枠)にあります。
※国税庁|令和7年分 給与所得者の基礎控除申告吉 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書を引用して加工
控除を受けたい従業員は、その年の最後の給与支給日の前日までに勤務先へ提出しなければなりません。
【源泉徴収簿を使用する場合】
源泉徴収簿を使用している場合は、2025年(令和7年)分の様式には特定親族特別控除の欄が設けられていないため、控除額を余白部分などに記載します。
※国税庁|令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)を引用して加工
記入漏れを防ぐため、控除額の確認と記載位置を事前に把握しておくことが重要です。
【2026年1月1日以降に支給される分の源泉徴収】
給与や賞与、公的年金などの源泉徴収での特定親族特別控除の適用は、2026年1月1日以降の支給分から始まります。
※国税庁|令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を引用して加工
2026年以降は、月々の給与計算にも新制度が反映されるため、適用開始時期を正確に把握し、円滑な運用を進めましょう。
特定親族特別控除に関する注意点
特定親族特別控除を適用する際は、控除対象者の範囲や所得要件、申告方法などを正しく理解しておくことが重要です。誤った申告を防ぐために、次の点に注意しましょう。
以下で、それぞれのポイントを解説します。
対象当否は申告年の12月31日時点の年齢で判断する
特定親族特別控除の対象となる親族は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であることが条件です。
例えば、早生まれで2026年2月に19歳になる大学生の場合、2025年12月31日時点ではまだ18歳です。そのため、2025年分の申告では年齢要件を満たさず、特定扶養親族として控除の対象にはなりません。
特定親族が非居住者の場合は別書類が必要になる
特定親族特別控除(2025年分以後の所得税に適用)の適用を受ける居住者は、年末調整の際、「親族関係書類」と「送金関係書類」を給与等の支払者に提出または提示する必要があります(外国語の書類には、日本語の翻訳文が必要)。
親族関係書類は、非居住者である親族との関係を証明するものです。日本国発行の戸籍の附票などを用いる場合、非居住者である親族の旅券(パスポート)の写しの提出または提示が求められます。旅券の写しを除き、原則として原本が必要です。
送金関係書類は、非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払をしたことを明らかにする書類です。
例えば、金融機関の為替取引書類(外国送金依頼書の控えなど)や家族カードの利用明細書、電子決済の移転に関する書類などが該当します。なお、現金で渡している場合などは、控除の適用を受けられません。
参考)国税庁|非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方
住民税は適用時期が異なる
個人住民税の適用は2026年度(令和8年度)から開始されますが、所得税の場合と比べると控除額は低く設定されています。
【特定親族特別控除額(個人住民税)】
参考)総務省|令和7年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について
特定親族特別控除の適用に向けた年末調整業務のポイント
特定親族特別控除は、年末調整に正しく反映させることが重要です。業務を円滑に進めるために、以下の点を押さえておきましょう。
以下で、それぞれのポイントについて見ていきます。
特定親族特別控除の仕組みを理解する
まず担当者自身が「特定親族特別控除」の仕組みを正しく理解することが重要です。控除対象となる親族の範囲や所得要件、従来の特定扶養控除との違いを把握しておくことで、従業員からの質問にも的確に対応できます。
また、制度の背景を理解しておくと、企業としての説明責任を果たしやすく、誤った案内を防ぐことにもつながるでしょう。
なお、年末調整では2025年分の所得税に適用され、例年とは異なる手続きが求められます。さらに、2026年1月1日以降の源泉徴収では、特定親族の合計所得金額が58万円超100万円以下の場合に適用されるため、制度の切り替え時期にも注意が必要です。
引用)国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
法改正について従業員に周知を促す
年末調整業務を円滑に進めるには、特定親族特別控除の制度内容を従業員に正確に伝えなければなりません。
控除対象となるのは大学生世代のアルバイトをしている子どもがいる従業員で、適用により納税額や労働条件に変化が生じる場合があります。そのため、必要書類や記入方法、提出期限などをまとめた文書を配布し、確認や質問に対応できる体制を整えておく必要があります。
従業員が制度を理解して正しく申告できるようにし、年末調整のミスや個別対応の手間を減らすようにしましょう。
給与計算ソフトに法改正の内容を反映させる
給与計算ソフトや給与計算システムには、特定親族特別控除の改正内容を確実に反映させましょう。反映漏れがあると、年末調整で控除額の誤りや手続きの遅れが生じるおそれがあります。
まずは、現在使用しているシステムの提供元に確認し、控除額や所得要件の変更が反映されているかをチェックすることが大切です。
クラウドサービスを利用する場合も、過去データの利用可否や扶養親族の年収・控除額の計算に間違いがないかを確認する必要があります。
特定親族特別控除まとめ
特定親族特別控除は、大学生世代の子どもを扶養する家庭を支援し、若年層の「働き控え」を解消する目的で創設されました。従来の扶養控除よりも所得要件が緩和され、子どもの収入が一定額を超えても控除を受けられる点が特徴です。
2025年分の所得税から適用され、年末調整では新たな申告書への対応が求められます。制度の理解不足やシステム未対応によるミスを防ぐため、早めに準備を進めましょう。