算定基礎届とは?対象者や提出先、提出方法をわかりやすく解説
更新日:2024年04月23日
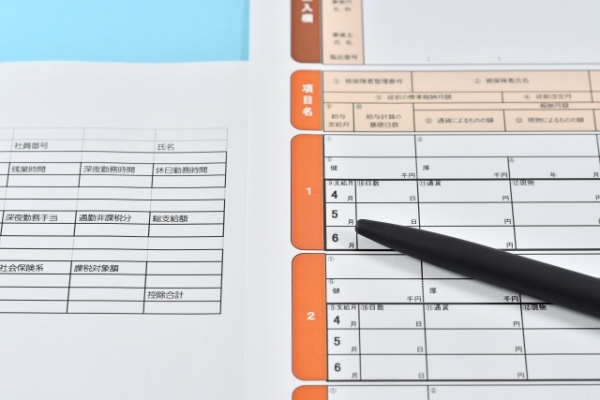
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
更新日:2024年04月23日
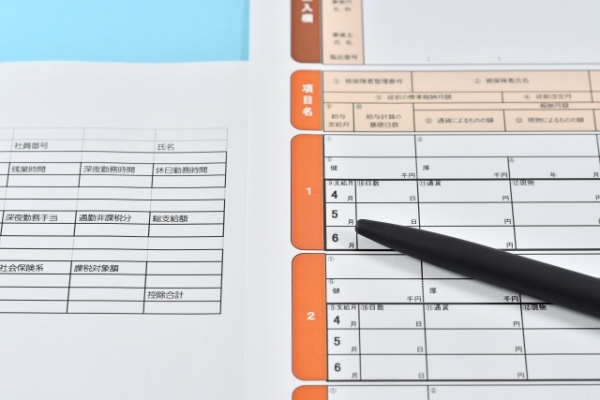
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
算定基礎届とは、従業員の報酬に基づき健康保険・厚生年金保険・介護保険の標準報酬月額を決定するための書類です。4月から6月の報酬月額をベースに、7月10日までに日本年金機構へ提出する必要があります。
本記事では、算定基礎届作成における報酬の計算方法や記入のしかた、提出方法について詳しく解説します。
目次
算定基礎届とは
「算定基礎届」は、健康保険および厚生年金保険の被保険者の「標準報酬月額」を定めるために、毎年7月に日本年金機構へ提出する書類です。標準報酬月額は、社会保険料を計算する際に必要なもので、4月から6月までに支払われた報酬の平均額に基づいて算出されます。
算定基礎届の提出対象は、7月1日時点で健康保険および厚生年金保険の被保険者となっている従業員です。ここでは、算定基礎届に基づく「定時決定」や「月額変更届(随時改定)」、算定基礎届の提出から社会保険料が決定するまでの流れについて解説します。
算定基礎届は「定時決定」で提出する書類
算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額を見直すために、毎年7月に日本年金機構に提出する書類です。「定時決定」とは、この見直しのことを指し標準報酬月額が実際の給与と大きな差が出ないようにするためのものです。
標準報酬月額は、社会保険料を計算するために必要なもので、4月から6月に支払われた給与の平均額に基づいて算出されます。事業主は、毎年7月10日までに算定基礎届を日本年金機構に提出しなければなりません。
日本年金機構は、提出された算定基礎届の内容をもとに報酬を等級ごとに分けた「標準報酬月額」を算出し、これに基づいて9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、企業と従業員が半分ずつ負担し、従業員の給与から毎月自動的に引き落とされます。
月額変更届(随時改定)との違い
「月額変更届(随時改定)」とは、固定的な給与や手当などが大きく上下した場合に、標準報酬月額を修正するための書類であり、毎年特定の時期に提出する「算定基礎届」とは異なる手続きです。随時改定が必要になるのは、従業員の昇給や降給などで固定的賃金が変わり、そのために現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が一年中続くと予測される場合です。
この場合には随時改定を実施し、変更後の固定的賃金が発生した月から数えて4か月目からの保険料をあらためて決めます。さらに8月や9月に随時改定をする場合、本来は毎年7月10日までに出さなければならない「算定基礎届」の提出省略の申請を行い「月額変更届」を提出します。
算定基礎届の提出から社会保険料が決定するまでの流れ
社会保険料が決定するまでの手続きは以下のとおりです。
なお、事業所は受け取った標準報酬月額決定通知書の内容を各従業員に伝える義務があります。従業員への通知を正当な理由なく省略した場合、最大で6か月の懲役または50万円の罰金を科される可能性があるため、注意が必要です。
算定基礎届の対象者
算定基礎届(定時決定)の対象者とは、7月1日現在で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員(休職中、海外出張中含む)です。
ただし、以下の条件に該当する場合は算定基礎届の対象外となります。
標準報酬月額の対象となる報酬、ならない報酬
一般的に給与が増加すると、保険料もそれに伴って増加するとされています。しかし、給与が必ずしも高額でない場合であっても、手当などが手厚い企業では標準報酬月額と社会保険料が予想以上に高くなる可能性があります。
標準報酬月額の計算には「対象となる報酬」と「対象外の報酬」が存在し、これらを理解することが重要です。ここでは、標準報酬月額にかかわる報酬について詳しく解説します。
対象となる報酬
労働者が得る報酬は、賃金・給料・俸給・手当など、すべてが含まれ形式を問いません。さらに、報酬は金銭(通貨)だけでなく、通勤定期券や食事、住宅などの現物支給も対象です。
たとえば、通勤定期券は全額が報酬に計上され、3か月や6か月分の定期券は、1か月分の金額に換算して報酬に加えます。食事の提供がある場合、厚生労働大臣が都道府県ごとに定めた金額をもとに換算します。ただし、従業員が1/3以下を負担している場合は、その負担分を差し引いた金額が報酬です。社宅や寮の提供も、都道府県ごとに設定された金額に基づいて報酬を計算します。
(勤務服でないもの)
※日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)」を引用し加工
対象とならない報酬
一時的な収入や臨時的な収入は、標準報酬月額に含まれません。年3回以下のボーナスや決算手当、出張の旅費など、定期的に支給されない金銭的収入も同様に標準報酬月額の対象から除外されます。また突発的な出来事に対する一時的な支払いや祝金なども定期的ではないため、標準報酬月額には含まれません。あわせて退職金も一度きりのため対象外です。
(業務に要するもの)
※日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)」を引用し加工
標準報酬月額の計算方法
標準報酬月額を計算する手順は、以下のとおりです。
こうして算出された保険料は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。ここでは、標準報酬月額を計算するそれぞれの手順について解説します。
1.4月・5月・6月に支払った報酬を確認する
標準報酬月額の基となる報酬は、実際に支払われた金額ではなく納税額を含む給与総額です。原則として4月から6月の間に支払われた給与総額を基礎として計算します。また基本給だけでなく、定期的に支払われる金銭も標準報酬月額に含めなければなりません。
「4月から6月の間に支払われた給与総額」は、たとえば3月分の給与が翌月の4月に支払われる場合には、4月に支払われる給与が標準報酬月額の基礎に含まれます。一方で6月分の給与は、7月に支払われるため含まれません。
2.各月の支払基礎日数を調べる
支払基礎日数は、報酬の支払い対象となる日数のことを指します。正社員は暦日数、パートやアルバイトなどの「短時間就労者」は出勤日数(有給休暇も含む)が支払基礎日数に該当します。給与計算の締切日と支払日により、支払基礎日数は変わるため注意が必要です。たとえば、25日締めの場合、4月の給与の支払基礎日数は3月26日から4月25日の31日となります。
3.3か月分の報酬の平均額を計算する
標準報酬月額は、4月から6月の3か月間の給与合計を3で割ることによって平均値を算出します。
【例】
この場合の計算式は「(33万円+30万円+27万円)÷3=30万円」です。したがって、3か月間の給与の平均額(標準報酬月額)は30万円となります。
4.3か月分の報酬の平均額を、管轄する都道府県の保険料額表から割り出す
「保険料額表」の標準報酬欄の等級と月額を参照し、4月から6月までの報酬の平均額がどこに該当するかを確認します。標準報酬月額は以下のように分けられ、健康保険料の率は都道府県ごとに異なります。
協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、該当する健康保険組合のホームページを参照してください。
※全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」(東京都)を引用し加工
算定基礎届の書き方
※日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」を引用し加工
算定基礎届の用紙には、5月19日時点で登録処理されている被保険者については、氏名・生年月日・従前の標準報酬月額などが印字されています。氏名などが印字されていない場合は、空欄に記載しましょう。ここでは一般的な算定基礎届について解説します。
一般的な例では、下表のとおり「支払基礎日数」「報酬(通貨+現物)」を計算し、報酬月額を算出したうえで「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入していきます。
(⑪+⑫)
⑮平均額(報酬月額)=(288,000円+288,000円+288,000円)÷3=288,000円
以下、それぞれの記入欄について詳しく解説します。
「日数」欄に支払基礎日数を記入する
算定基礎届は、報酬月額として4月、5月、6月に支給された給与を申告します。ただし、給与の計算期間の終了日と支払日の関係により、支払いの基準日数は異なるため注意が必要です。
【支払基礎日数】
当月末日支払
当月末日支払
翌月10日支払
「通貨」「現物」「合計」欄を記入する
「⑪通貨」「⑫現物」「⑬合計」の各欄には、支払基礎日数に対応する通貨や現物での報酬、その合計を記入します。通貨は、基本給や手当など現金で支払われる報酬です。
自社製品やその他の形で支給される現物については、基本的には時価に換算して計算します。食事や住宅の場合は、日本年金機構の「全国現物給与価額一覧表」(地域や年度により金額は異なります)をもとに、1か月換算の金額を記入します。
欠勤控除などで支払基礎日数が17日未満の日がある場合、その月は標準報酬月額の算出には含みませんが、その場合であっても支給額と現金支給は記入するようにしましょう。
(単位:円)
(⑪+⑫)
※全国健康保険協会「日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」を引用し加工
「総計額」欄を記入する
「⑭総計欄」には、支払基礎日数が17日以上の月すべての通貨と現物の合計額を転記します。
(単位:円)
(⑪+⑫)
「平均額」欄に総計額を対象月数で割った額を記入する
「⑮平均額」欄には、4月から6月(支払基礎日数が17日以上)総計の平均値を記入します。
(単位:円)
(⑪+⑫)
⑮平均額(報酬月額)=(288,000円+288,000円+288,000円)÷3=288,000円
仮に5月の支払基礎日数が17日未満の場合には、「⑭総計欄」に5月分を含めずに4月と6月(支払基礎日数が17日以上)の合計を記入し、それを2で割って平均額を算出します。
(単位:円)
月給制・毎月20日締、当月25日支払
(⑪+⑫)
⑮平均額(報酬月額)=(288,000円+288,000円)÷2=288,000円
【ケース別】算定基礎届の書き方
ここまで算定基礎届の一般的な書き方について解説してきましたが、ここからは以下のケースごとに詳しく解説します。
パートやアルバイトの場合
短時間労働者(パートタイマー)の報酬月額は次のように決定します。
(1)のケース
4月・5月・6月分が対象です。
報酬月額=(135,000円+142,500円+127,500円)÷3=135,000円
(2)のケース
6月分のみが対象です。
報酬月額=127,500円(6月分)
(3)のケース
5月と6月分が対象です。
報酬月額=(112,500円+120,000円)÷2=116,250円
(4)のケース
報酬月額=従前の標準報酬月額
【(1)のケースの記載例】
※日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」を引用し加工
途中入社した場合
4月の途中で入社した場合、日割り計算で給与が支払われたとしても、1か月分全額の給与支払いではないため、1か月分全額の給与が支払われない月は算定対象月から除かれます。
たとえば「毎月20日締、翌月10日支払」のケースでは、4月の途中から入社した場合、1か月分全額の給与支払いになるのは6月給与分からです。したがって、6月給与のみが報酬月額となります。
4月途中での入社のケース(毎月20日締、翌月10日支払)
6月分のみが対象です。
報酬月額=200,000円(6月分)
【途中入社した場合の記載例】
※日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」を引用し加工
一定期間全く報酬を受けていない場合
病気や欠勤・育児休業・介護休業などにより、4月から6月までのどの月も報酬が全く支給されなかった場合には、従前の標準報酬月額が適用されます。
また、4月から6月までのどの月も支払基礎日数が17日未満(短時間就労者の場合は15日未満、短時間労働者の場合は11日未満)である場合も同様に、従前の標準報酬月額です。
【一定期間全く報酬を受けていない場合の記載例】
※日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」を引用し加工
随時改定を予定している場合
「定時決定」によって決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月までの1年間適用されます。ただし、昇給や降給などにより報酬が大きく変動した場合には、次回の定時決定を待つことなく、実態に合わせて標準報酬月額を見直します。これを「随時改定」といい、「月額変更届」の提出を行わなければなりません。
改定後の標準報酬月額は、再度の随時改定が行われない限り、改定が6月以前に行われた場合はその年の8月まで、7月以降に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。これにより、報酬の実態と標準報酬月額との間に大きな乖離が生じることを防ぎます。
【随時改定を予定している場合の記載例】
※日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」を引用し加工
4月~6月が繁忙期にあたる場合
4月から6月までの繁忙期に残業が増え、標準報酬月額が上昇することもあります。このようなときは、「4月〜6月の給与に基づく標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与に基づく標準報酬月額」を比較します。保険料額表で2等級以上の差が出る場合、前年の7月から当年の6月における標準報酬月額での決定が可能です。
この適用を受けるには「事業主の申立書」と「被保険者の同意書」の提出が必要です。希望する場合は「8.年間平均」に◯をつけます。
休業手当が支払われた場合
一時的な帰休により、通常の労働報酬よりも少ない休業手当が支給される場合は「随時改定」の対象のため、一時帰休により決定または改定される前の標準報酬月額で決定します。7月1日時点における「一時帰休状態」が続いているかどうかによって、記入方法が異なります。
【7月1日時点で一時帰休状態が続いている場合】
報酬月額=(270,000円+270,000円+180,000円)÷3=240,000円
一時帰休による休業手当が支払われた月だけでなく、通常の給与を受け取った月も合わせて報酬月額を計算します。「9.その他」に◯をつけ、休業手当の支払月と一時帰休の期間(開始したときは「〜月〜日から一時帰休」)と記入します。
【7月1日時点で一時帰休が終了している場合】
報酬月額=(270,000円+270,000円)÷2=270,000円
休業手当の含まれない月の給与が、対象です。また、4月・5月・6月のすべての月で休業手当が支払われていた場合、「一時帰休により低額な休業手当等に基づいて決定または改定される前の標準報酬月額」で計算します。「9.その他」に◯をつけ、休業手当の支払月と一時帰休の期間(解消したときは「◯月◯日一時帰休解消」など)と記入します。
賞与などが年4回以上支給された場合
賞与が前年の7月から当年の6月までの間に4回以上支給された場合、賞与の合計額を12で除算し、その金額を毎月の給与に追加して、月々の報酬を計算します。
たとえば、1年間で賞与が4回、合計120万円支給されたとします。この120万円を12か月で除算すると、1か月あたり10万円です。この10万円を4月、5月、6月の各月の総支給額に加えます。
「9.その他」に◯をつけて、賞与の支払い月とその合計額を12か月で除算した金額を記入します。
算定基礎届の提出先
毎年7月10日までに、日本年金機構の事務センター、または管轄の年金事務所へ算定基礎届を提出します。健康保険組合、厚生年金基金、企業年金基金に加入している場合には、そちらにも算定基礎届を出します(例:関東ITソフトウェア健康保険組合)。
算定基礎届の提出方法
算定基礎届の提出方法には、直接持参、郵送、電子申請(e-Gov電子政府の総合窓口)があります。2020年4月からは新しい電子申請gBiz(ジービズ)による提出もできるようになりました。また、電子データで作成した届出を電子媒体(CD/DVDなど)へ保存して提出も可能です。ただし、総括表は電子媒体での提出が認められていません。総括表を電子申請する際には、画像ファイルとして添付します。画像ファイル形式も決められており、JPEG、PDFであれば受け付けてもらえます。
電子申請が便利に
資本金が1億円を超える特定の法人などは、2020年4月から社会保険の一部手続きで、電子申請が義務化されました。それにあわせて電子申請も便利になり、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)とは別に、前述したgBiz(ジービズ)での手続きが開始されました。
e-Govよりも手続きの種類は限られますが、申請書と印鑑証明書・印鑑登録証明書を郵送して無料のGビズIDを取得すれば、電子証明を取得しなくても、日本年金機構Webサイトから「社会保険届書作成ソフト」をダウンロードし、電子申請を始められます。
gBizは社会保険であれば「資格取得届」「被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」「資格喪失届」「算定基礎届」「月額変更届」「賞与支払届」をオンラインで手続きできます。中小企業や個人事業など、電子申請が義務ではない事業所でも、手軽に電子申請を始められるようになりました。
健康保険に関して政府管掌の都道府県・協会けんぽであれば、e-GovやgBizで厚生年金と合わせて1回の手続きで完了しますが、健康保険組合の場合は、別途、健康保険組合への提出が必要です。
算定基礎届まとめ
算定基礎届の作成は、対象となる従業員と標準報酬月額の基となる報酬を正確に理解し、期限内に提出することが重要です。提出期限は7月1日から7月10日までと短く、その間に全従業員の情報を漏れなく正確に記入しなければなりません。多忙さに追われながらも他の業務に影響を与えないよう効率的に進めることが求められます。
また2020年4月からは、特定の大企業に対して社会保険・労働保険の一部手続きの電子申請が義務化され、今後は中小企業への適用も予想されます。現状のシステムが電子申請に対応していない場合は、早めの準備が必要です。