2025年(令和7年)│扶養控除等(異動)申告書の書き方と注意点
更新日:2025年11月17日
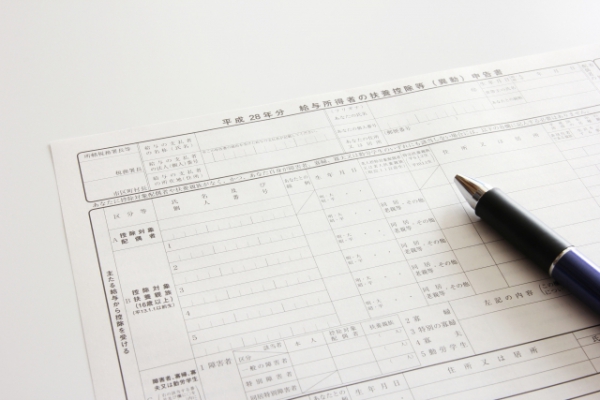
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
更新日:2025年11月17日
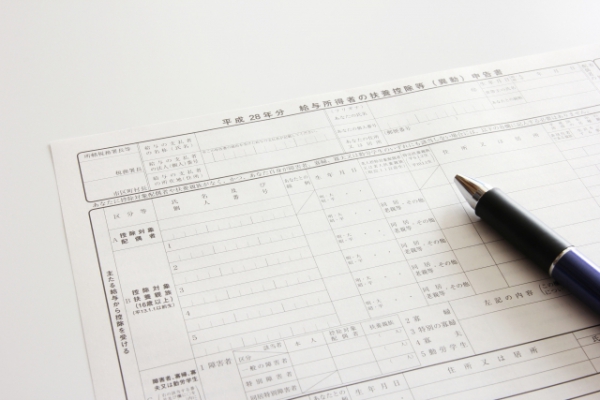
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
扶養控除等申告書は、年末調整で正確な税額を計算するために欠かせない書類です。2025年(令和7年)分からは、基礎控除や給与所得控除の見直しに加え「特定親族特別控除」が新設されるなど、記入内容にも変更点があります。
年末調整を担当している方の中には、「今年は何が変わったの?」「書き間違えないか不安」という方も多いのではないでしょうか。本記事では、改正のポイントと正しい書き方、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
目次
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整の際に勤務先に提出する重要な書類です。この申告書は、給与所得者が所得控除を受けるために必要なものであり、略して「扶養控除等申告書」「マル扶」などと呼ばれます。
扶養控除や配偶者控除をはじめとするさまざまな控除を申請するために、この書類の提出が必要です。書類の内容をもとに正確な税額が計算されます。
扶養控除等申告書の提出者
扶養控除等申告書の提出者には、一般社員だけでなくパートやアルバイトなど給与を得ているすべての給与所得者が含まれます。この申告書は、扶養控除の計算が必要かどうかを確認するためのものであり、扶養親族がいない場合でも提出を求められます。
ただし、給与収入が2,000万円を超える人やすでに退職している人など年末調整の対象外となる場合は、扶養控除等申告書の提出は不要です。
扶養控除の対象
扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在で16歳以上の人を指します。
扶養親族は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
なお、納税者が年の途中で死亡または出国する場合は、その時点での状況で判断されます。
さらに、次のすべての条件に当てはまる場合は、新たに創設された「特定親族特別控除」の対象になります。
(給与所得のみの場合は収入123万円超188万円以下)
「扶養控除」と「配偶者控除」の違い
「扶養控除」と「配偶者控除」は、いずれも所得控除の一種ですが、対象となる人に違いがあるため注意しましょう。
扶養控除は、16歳以上の扶養親族を対象としており、その要件を満たす家族がいる場合に適用されます。
「配偶者控除」は配偶者に対して適用される控除です。適用を受けるためには、配偶者の年間所得が令和7年分以後は58万円以下(給与収入のみは年収123万円以下)であり、さらに納税者と生計を一にしている必要があります。また、「配偶者特別控除」という仕組みもあり、これは配偶者の所得が令和7年分以降は58万円超~133万円以下(給与収入のみは年収123万円超〜201.6万円未満)の場合に段階的に控除額が適用される制度です。ただし、どちらの控除も、納税者本人の年間合計所得が1,000万円を超えると適用されません。
扶養控除等申告書を提出するタイミング
扶養控除等申告書は、その年の最初の給与支払日前日までに提出しなければなりません。中途で就職した場合は、最初の給与支払日前日が提出期限です。
申告書に記入した内容に変更があった際は、その変更日以降、最初に給与が支払われる日の前日までに新しい内容について記入した申告書を提出する必要があります。
さらに、非居住者の親族に対する扶養控除や障害者控除を受ける場合は、その年の最後の給与支払日前日までに、その親族と生計を共にしている事実について記入した申告書を提出しなければなりません。
継続勤務中であれば、年末調整の時期に合わせて申告書を提出します。
扶養控除等申告書を提出しないとどうなる?
扶養控除等申告書は、年末調整時に必ず渡される重要な書類であり、提出しないケースは少ないでしょう。しかし、もしこの申告書を提出しなかった場合には、さまざまな影響が生じてしまうため注意してください。
まず、所得税の控除を受けられず、結果として税金が高くなります。また、自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告もしなかった場合には、罰則が科される可能性もあり、その結果、支払う税金がさらに増えてしまうことも考えられます。
そのため、扶養控除の対象となる家族がいない場合でも、必ず申告書を提出するようにしましょう。
2025年(令和7年)年末調整4つの変更点
令和7年度の税制改正では、所得税に関する大幅な見直しが行われました。主な改正は、以下の4つです。
これらの改正は2025(令和7年)分以降の所得税に適用され、令和7年12月に実施する年末調整から影響します。
令和7年11月までの源泉徴収事務は従来どおりですが、年末調整では改正後の内容で所得税額を再計算しなければなりません。各種申告書の提出もれがないよう、事前の準備が必要です。
1.基礎控除額の引き上げ
基礎控除は、すべての居住者が所得から差し引ける基本的な控除です。今回の改正では、合計所得金額に応じて控除額が段階的に設定されました。
たとえば、合計所得金額が132万円以下(給与収入が200万3,999円以下)の場合、控除額は95万円です(改正前は48万円)。この控除額95万円は、改正後の基礎控除額58万円に加算額37万円を加えた控除額となります。
所得が増えるほど控除額は段階的に減少し、合計所得金額が2,350万円を超えるケースでは、従来との変更はありません。
参考)国税庁|令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
2.給与所得控除の引き上げ
給与所得控除の最低保障額も引き上げられました。これまでの55万円から65万円へ引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合に65万円の控除が適用されます。
なお、給与の収入金額が190万円を超える場合は、変更がありません。改正前と同じ控除額(下表のとおり)です。
この改正後の控除額を反映して合計所得金額を算出し、申告書に正しい金額を記載する必要があります。
参考)国税庁|令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
3.特定親族特別控除の創設
令和7年度の税制改正では、「特定親族特別控除」が創設されました。特定親族特別控除は、大学生年代の子どもなど一定の所得を得ている若年層の親族を扶養する家庭の支援を目的とした制度です。
特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族をいいます(児童福祉法に基づき養育を委託された里子を含む)。
ただし、以下に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下であることが条件です。
控除額は、合計所得金額に応じて異なります。58万円超85万円以下(給与収入のみは123万円超150万円以下)の場合は、63万円の控除です。
85万円超123万円以下(給与収入のみは150万円超188万円以下)の場合は、控除額が段階的に減少します。
引用)財務省|令和7年度税制改正
特定親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみは123万円以下)の場合は、特定親族特別控除の対象外ですが、従来どおり「特定扶養親族」として扶養控除(控除額63万円)の対象です。
参考)国税庁|令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
4.扶養親族等の所得要件の引き上げ
基礎控除額の見直しに伴い、扶養控除や配偶者控除などの対象となる親族の所得要件も改正されました。
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子の所得要件は、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられています。
また、勤労学生の所得要件も75万円以下から85万円以下に変更されました。
扶養控除等申告書の書き方
扶養控除等申告書は、給与所得者が毎年提出する重要な書類です。この申告書を正確に記入することで、適切な所得税の源泉徴収や住民税の計算がなされます。
しかし、多くの人にとって、この書類の記入は複雑で難しいものと感じられがちです。ここでは、扶養控除等申告書の各項目について、わかりやすく解説します。
記入項目は、以下のとおりです。
実際の扶養控除等申告書を見ながら、記入方法を確認しましょう。
1.基本情報
扶養控除等申告書の最上部は、年末調整を受けるすべての従業員が記入すべき基本情報です。以下の項目を記入しましょう。
個人番号の記入は、勤務先によって不要な場合があるため、確認するようにしましょう。扶養対象の配偶者や親族がいない場合は、基本情報のみを記入し、勤務先に提出すれば問題ありません。
2.源泉控除対象配偶者
Aの源泉控除対象配偶者の欄には、以下の内容を記入します。
所得の見積額は、年間の収入から必要経費を差し引いて算出します。給与所得の場合は、給与所得控除が必要経費です。また、公的年金等控除額も差し引きます。
たとえば、配偶者がパートタイムで年間103万円の給与収入を得ている場合、所得額の計算は次のようになります。
年間の収入額1,030,000円から給与所得控除額650,000円を引くと、給与所得額は380,000円です。この場合、申告書には「380,000」と記入します。
3.控除対象扶養親族
当年末時点で16歳以上であり、その年の所得の見積額が58万円以下(年収123万円以下)である同一生計の親族がいる場合に書き込む欄です。
扶養親族が非居住者の場合は、親族関係書類と送金関係書類の添付が必要です。
4.障害者、寡婦・ひとり親又は勤労学生
扶養控除等申告書には、特別な状況に応じた控除項目があります。ここでは、障害者、寡婦・ひとり親、勤労学生に関する控除の記入方法について解説します。
障害者
障害者控除を申告するには、以下の手順で記入します。
寡婦・ひとり親
扶養控除等申告書の「寡婦・ひとり親」の欄は以下の手順で記入します。
勤労学生
扶養控除等申告書の「勤労学生」の欄は、以下のように記入します。
勤労学生控除は、一定の条件を満たす学生が対象であり、控除を受けるためには給与所得やその他の所得に制限がある点に注意しましょう。
5.他の所得者が控除を受ける扶養親族等
同一世帯に複数の所得者がいる場合、扶養親族を重複して申告することはできません。たとえば、夫婦が共働きで子どもがいる場合、子どもを扶養親族として控除できるのは、夫か妻のどちらか一方のみです。
このような場合、もう一方の所得者は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の欄に、扶養親族である子どもの氏名と控除を受ける所得者の情報(たとえば夫または妻の氏名)を記入します。
6.住民税に関する事項
「住民税に関する事項」欄は、以下の条件に該当する場合に記入が必要です。
扶養控除等申告書で確認できる控除の種類
毎年の年末調整や確定申告の時期になると、多くの人が「扶養控除等申告書」と向き合うことになります。この申告書は、個人の所得税を正確に計算するために欠かせない重要な書類です。しかし、その内容は複雑で、どの控除が自分に適用されるのか判断に迷う方も少なくありません。
この申告書を通じて確認できる控除には、さまざまな種類があります。配偶者や扶養家族に関する控除、障害者や特定の家族状況に対する控除など、個人の生活状況に応じた多様な控除が用意されているため、確認しておきましょう。
具体的には、以下のとおりです。
ここでは、扶養控除等申告書で確認できる主な控除の種類について、詳しく解説します。
配偶者控除・配偶者特別控除
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、納税者本人の合計所得が1,000万円を超えない場合に適用される税制上の優遇措置です。
配偶者控除(図の左上)
控除対象となる配偶者は、合計所得金額が58万円以下(給与収入のみは123万円以下)の人です。配偶者が70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」として控除額が高くなります。
配偶者特別控除(図の右上と下)
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象外となるケースであっても、配偶者の所得が一定範囲内であれば受けられる控除です。
具体的には、配偶者の年間所得が58万円超~133万円以下(給与収入で123万円超~201.6万円未満)の場合に適用され、所得の額に応じて控除額が段階的に変わります。
また、配偶者がその年に青色申告の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告の事業専従者でないことも要件に含まれます。
参考)国税庁|No.1191 配偶者控除
参考)国税庁|No.1195 配偶者特別控除
扶養控除
扶養控除は、申告者本人に扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。扶養親族には、納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族や里子、養護を委託された高齢者などが該当します。
扶養親族となるためには、年間の所得が548万円以下(給与収入のみの場合は1203万円以下)であることや、青色申告者の事業専従者として給与を受けていないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。また、控除対象となる扶養親族は、年齢が16歳以上であることも必要です。
控除額は、以下のとおりです。
参考)国税庁|No.1180 扶養控除
障害者控除
障害者控除は、納税者本人や同一生計配偶者、または扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除の制度です。
控除額は一律ではなく、障害の程度に応じて異なり、重度と認定された場合は「特別障害者控除」としてより大きな控除額が適用されます。
年末調整や確定申告の際に、所定の申告書を提出することで、この控除を受けられます。
参考)国税庁|No.1160 障害者控除
寡婦控除
寡婦控除は、離婚や死別後に再婚していない女性を対象とする所得税および住民税の控除制度です。
この控除を受けられるのは、民法上で婚姻関係にあった夫と離婚または死別した女性であり、一定の条件を満たした場合に適用されます。
控除額は令和2年(2020年)から27万円 に統一されており、寡婦控除を受けるためには、年末調整や確定申告での申請が必要です。これにより所得税や住民税の負担が軽減されます。
ひとり親控除
ひとり親控除は、令和2年(2020年)分から導入された新しい控除制度です。それ以前は未婚のひとり親が所得控除を受けられませんでしたが、この控除が設けられたことで、該当者が控除を受けられるようになりました。
ひとり親控除を利用できるのは、12月31日時点で婚姻していない、もしくは配偶者の生死が不明な人で以下の3つの条件を満たしている場合です。
控除額は、子どもの人数にかかわらず一律で所得税35万円、住民税30万円 です。
会社員の場合は年末調整、自営業などの方は確定申告で適用を受けられます。
勤労学生控除
勤労学生控除は、学業と仕事を両立する学生の税負担を軽減する制度です。アルバイトなどで給与所得を得ている学生本人が対象で、一定の条件を満たすことで所得税や住民税の負担が減ります。申告の際は、以下の3つの要件をすべて満たしているか確認することが重要です。
アルバイトやパートなど、働いて得た給与所得が対象です。親からの仕送りや奨学金は勤労による所得には含まれません。
合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下でなければなりません。給与所得のみの場合、年収が150万円以下であればこの条件を満たします。
学校教育法に定められた大学や高等専門学校、一定の専修学校・各種学校、または職業訓練法人の認定訓練に通う学生が対象です。該当するか不明な場合は、在籍校で確認しましょう。
勤労学生控除を受けると、所得税で27万円の控除が受けられ、住民税についても控除(一般的に26万円程度)が適用されるため、全体的な税負担を抑えられます。
ただし、この控除は学生本人が対象であり、学生を扶養している親は利用できません。要件を満たしていない場合は申請が認められないため、事前に条件を確認してから申告書を記入するようにしましょう。
2025年(令和7年)法改正による年末調整業務の注意点
令和7年度の税制改正では、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設など年末調整に直接影響する変更が複数導入されました。
これらは2025年(令和7年)12月の年末調整から適用されるため、担当者は改正内容を正確に理解し、システムへの反映や従業員への周知を早めに進める必要があります。
ここでは、実務上押さえておくべき注意点を解説します。
法改正について従業員に周知する
令和7年度の税制改正により、扶養親族等に関する所得要件が引き上げられました。そのため、従業員には新たに控除対象となる親族がいないか確認を促す必要があります。
該当者には「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出に加え、記載内容に誤りがないよう正確に記入してもらうよう依頼することが大切です。また、特定親族特別控除の創設に伴い、適用を希望する従業員には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出も求めてください。
これらの申告書が未提出の場合、控除が適用されず従業員の税負担が増えるおそれがあります。改正内容を社内で周知し、対象者が適切に手続きできるよう案内することが重要です。
控除額の計算ミスに気を付ける
令和7年分の年末調整では、以下の点に注意が必要です。
なお、「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、特定親族特別控除の適用がある場合の計算に未対応のため、余白欄を使用するなどして計算します。
また、特定親族特別控除を適用する場合は、その控除額を給与所得の源泉徴収票に記載する必要があります。
※国税庁|令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)を引用して加工
年末調整に向けゆとりあるスケジュールを組む
年末調整を円滑に進めるには、扶養控除等申告書の提出期限を早めに設定し、ゆとりをもったスケジュールを組むことが重要です。
回収が遅れると、記入もれや不備の確認が後ろにずれ込み、再提出の手配などで担当者の負担が増すおそれがあります。特に、令和8年分以降は源泉控除対象親族の記載内容が改正され、申告書の様式も変更されるため、従業員への早期周知が欠かせません。
実務では12月中旬の期限を待たず、可能な限り前倒しで書類を回収するとよいでしょう。税務署への提出や修正の対応に余裕が生まれることから、全体の進行がスムーズになります。
また、新入社員については初回の給与支給前に申告書の提出が必要となるため、入社時の案内段階で明確に伝えておくようにしましょう。
法改正の内容をシステムに反映させる
法改正に対応した年末調整を正確に進めるには、利用している年末調整システム(年末調整機能がある給与計算ソフトも含む)への反映確認が重要です。まず、基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件など、改正点が正しく反映されているかをチェックしましょう。
クラウド型システムでは自動更新される場合が多いものの、過去データの参照可否はサービスによって異なります。過去の申告情報を利用できない場合は扶養親族の所得や控除額を手動で確認し、誤りを防ぐ体制を整えるようにしましょう。
扶養控除等申告書まとめ
2025年(令和7年)の税制改正では、基礎控除や給与所得控除の引き上げに加え、「特定親族特別控除」の創設など大きな変更がありました。扶養控除等申告書を正確に記入し、必要書類を期限内に提出することで、適切な控除を受けられます。
年末調整をスムーズに進めるには、早めに従業員へ法改正の内容を周知し、給与計算システムへの反映状況を確認しておくことが重要です。ゆとりあるスケジュールで年末調整に必要な申告書類を回収し、年末調整業務の円滑化を図りましょう。